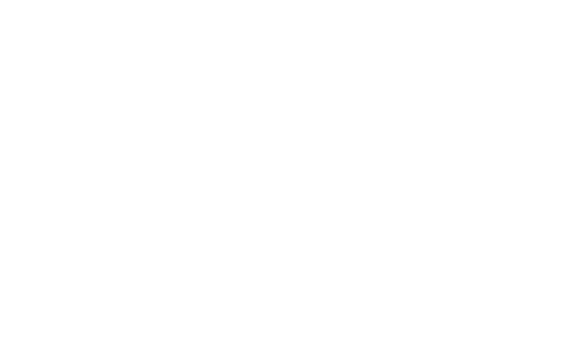
浮田弘美先生 失語症塾 非流暢性失語症へのアプローチ
- 日時
- 2025/02/14 (金)19:00 - 20:30 JST
- 場所
- オンライン
- 講師
- 浮田弘美先生
- 参加費
- セミナー参加権(脳ケアゼミ会員は無料)
¥2,000
詳細
理想的には初回評価で失語症と鑑別をすると同時に流暢性/非流暢性の判断をします。しかし、初回だけ、それも20~30分程度では判断しきれないかもしれません。なぜなら、当たり前のことですが、流暢かどうかの判断は発話を聞いてみなければ分からないから。まさに「話さなければ分からない失語症」です。非流暢性失語についてはいろいろな考え方があるようですが、「非流暢性失語≒発語失行(失構音)を伴う失語」と捉えるのが最も分かりやすいと思います。そこで、今回は、まず発語失行そのものについてお話したうえで、非流暢性失語(発語失行を伴った失語症)へのアプローチを臨床経験に基づいて具体的にお話いたします。
*セミナー割引が受けられるリジョブメルマガはこちらから
ぜひご登録下さい
https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=rejob_osaka&task=regist
講師
浮田弘美先生
津田塾大学、同大学院博士課程前期修了。
国立身体障害者リハビリテーションセンター学院聴能言語専門職員養成課程を卒業後、民間病院勤務を経て1990年~2020年大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部にて臨床・教育・研究に従事。
その間に言語聴覚士が国家資格となり、1999年言語聴覚士免許取得。
臨床40年を経た現在、言語聴覚士の後進指導・育成に携わっている。

